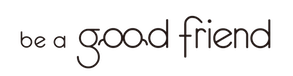Domaine Fischbach “Jean Dreyfuss” – Chap.11

フランスでとてもうまくいっている新しいキュヴェがあるんだ。よかったら、その隙間にどうかな?
Jean Dreyfuss / ジャン ドレフュス
送られてきたのは、一枚の写真だけ
「普段はあまりこういうことはしないんだけど」
いつものようにメールでワインを注文し、パレットに少しばかりスペースが残っている、そんな状況でのこと。
ドメーヌ フィッシュバックのジャン ドレフュスが、少しばかりためらいがちに切り出した。
「フランスでとてもうまくいっている新しいキュヴェがあるんだ。よかったら、その隙間にどうかな?」
送られてきたのは、ワインの名前と品種、値段、それから彼が友人たちと楽しげに飲んでいる写真だけ。
飲んだことのないワインを、それだけの情報で買うべきか。インポーターとしては悩ましいところ。
でも、わたしは「イエス」と答えた。
なぜなら、いつもは控えめで、こちらの判断を静かに尊重してくれる彼が、そんな風に何かを薦めてくること自体が、ひとつの確かなメッセージのように思えたから。
これは、「いい人だから買う」というのとは、少しばかりわけが違う。
最初のヴィンテージから、ずっと彼の仕事を見てきた。その長い付き合いの中で、ジャンという人間を少しづつ理解してきたし、もちろんワインの造り手としても信頼を重ねてきた。
そんな彼からの「控えめな提案」というのは、単純に期待できると思ったから。

高貴な日常
この新しいワインを理解するために、アルザスの伝統について少しだけ整理しておく必要がある。
アルザスといえば、フランスの他のワイン産地とは異なり、少し「堅い」イメージがある産地。ボトルは細長く、この地域のトップワインには、畑名と単一の品種名が誇らしげに刻まれている。
それが今のアルザスの伝統。
しかしこの伝統は、ここ100年か200年くらいの間に生まれた新しい伝統なのではと思う。
フィロキセラという害虫がヨーロッパ中の畑を壊滅させた19世紀。その惨事のあとには、畑は植え替えを迫られた。
では、それ以前はどんな景色が広がっていたんだろう。
農薬を含む農業技術の発達が今ほどでなかった時代。その頃は、様々な品種を一緒に植える「混植」が当たり前だったんじゃないだろうか。
1つの区画に1つの品種を植えるというのは、病害・天候・生育不良によって収穫を一度に失いかねないリスクを背負うことになる。
一方で「混植」は、ある品種が病気になっても、他の品種が生き残る。それは、今以上に自然と対話し、共生しなければいけない時代の合理的な知恵だったといえる。
そんな古い伝統の名残を感じるワインが、アルザスにはある。
かつては、単に「ツヴィッカー(ブレンド)」と呼ばれ、シャスラやシルヴァネールといった収量が多く一般的なブドウ品種のみをブレンドしたシンプルなワインだったものが、リースリングやゲヴュルツトラミネールなどを加えることで、接頭辞として「エーデル(高貴な)」が付加された「エーデルツヴィッカー」だ。
そんな高貴なワインも新しい伝統では、日常的にがぶがぶ飲むための、エントリークラスのワインと見なされるようになっていった。
面白いことに、アルザスにはWinstub(ヴィンステュブ)という居酒屋があるらしく、この居酒屋では、このエーデルツヴィッカーが1リットルのでっぷりとしたボトルで出てくることがあるという。
みんなでテーブルを囲み、陽気に、気取らずに楽しむためのワイン。それが現代の「エーデルツヴィッカー」だ。
そして、ジャンが僕に送ってきたこの「リトロジェンヌ」もまた、その1リットルボトルに詰められていた。
つまりは僕らのまわりにある空気のようなもの
「リトロジェンヌ」は、VDF(ヴァン ド フランス)区分なので、「エーデルツヴィッカー」ではないけれど、コンセプトは間違いなく「理屈はいいから、みんなで楽しく飲んでくれ」というワイン。
品種は、ゲヴュルツトラミネールとオーセロワ、そしてリースリング。きちんと「高貴な」品種が使われている。
エチケット(ラベル)はどこかクラシックな趣だが、よく見ると車のスピードメーターを模した飲み心地メーターがあり、その針が振り切れている。「ボトルから直接飲むな」というユーモラスな注意イラストも描かれている。
「なるほどね。気軽でさっぱりしたワインなんだろうな。」と想像しながらグラスに注いで、いい意味で裏切られた。これは、イージーなワインなんかじゃない。焦点がぴしりと定まった、実に構成のしっかりしたワインだった。
心地よい苦みと、果実の柔らかな甘み。奥行きのある、リッチで華やかな香り。これは小ぶりなグラスでちびちびやるより、ブルゴーニュグラスのような、少し大きめのグラスでゆったりと空気を含ませながら飲むべきワイン。
感心のため息をつきながら、この「Litorogène」という不思議な名前について考えた。
ひとつは、1リットルボトルだから「Litre(リットル)」に何かを掛けた言葉だろう、ということ。では、何を?もう1つ思いついたのは「Nitrogène(ニトロジェンヌ)」、つまり「窒素」。
窒素は、地球の大気の約78%を占める、ごくありふれた気体。無味無臭で、僕らは普段その存在を意識することさえない。でも、植物が育つためには、それは絶対になくてはならないものでもある。
日々の暮らしの中に当たり前のように満ちていて、それでいて、なくてはならないもの。
もしかしたらジャンは、このワインがそんな存在になってほしい、と願ったんじゃないだろうか。
1リットルのボトルにたっぷりと詰められた、水のように、あるいは窒素のように、わたしたちの毎日を満たしてくれる存在。
これはジャン本人に確認したわけではなくて、あくまでわたしの、ほとんど根拠のない妄想のようなものだけど。

Litrogène Blanc / リトロジェンヌ ブラン

ヴィンテージ:NV (2023)
タイプ:白
産地:フランス アルザス地方
品種:ゲヴュルツトラミネール 40%、オーセロワ 40%、リースリング 20%
普段は控えめなドメーヌ フィッシュバックのジャン ドレフュスが、珍しく「フランスでとてもうまくいっている新しいキュヴェがあるんだ」とすすめてくれたキュヴェ。
Litorogène(リトロジェンヌ)という名前は、このワインが詰められた1リットルボトルを示す「Litre(リットル)」と、大気の約78%を占める「Nitrogène(窒素)」を想起させる名前で、「日々の暮らしの中に当たり前のように満ちていて、それでいて、なくてはならないもの。」を象徴してるように感じます。
ゲヴュルツトラミネール、オーセロワ、リースリングが生み出す香りは、リッチで華やか。口に含むと、心地よい苦味と果実の柔らかな甘みが絶妙なバランスを保ち、焦点がぴしりと定まります。定まった、しっかりとした構成を感じさせます。
アルザスの伝統的なアッサンブラージュ(ブレンド)ワインである「エーデルツヴィッカー」のように、仲間とテーブルを囲み、陽気に、気取らずに楽しんでほしい。そんな想いが、たっぷり1リットルのボトルに詰め込まれたワインです。
しかし、その本領は、ただ気軽に飲むだけのワインにとどまりません。ブルゴーニュグラスのような大きめのグラスで、ゆったりと空気を含ませながら、その複雑さと奥行きをじっくりと楽しんでいただきたい一本です。
このワインは、ビオロジックで栽培されたブドウを用い、自然酵母のみで発酵。厳密な濾過(ろか)や清澄も行わず、瓶詰め時に至るまで亜硫酸塩(酸化防止剤)も無添加で造られます。
他の多くのドメーヌ フィッシュバックのワインと同じく、抜栓後数日たってもバランスを崩すことなく、長く安定した味わいを楽しませてくれます。